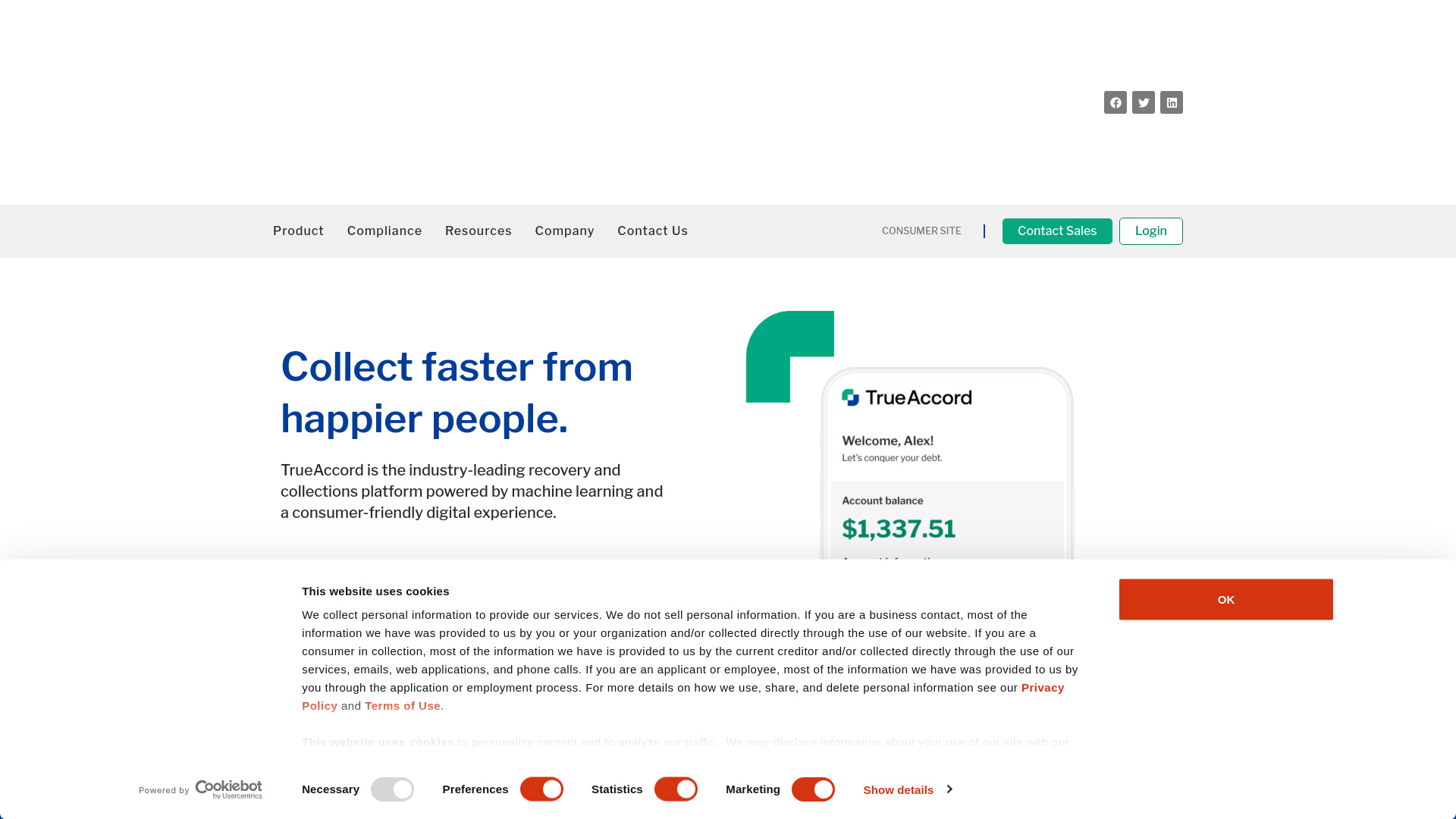
TrueAccord
ウェブサイトを開く-
ツール紹介:機械学習で債権回収を最適化。自助型デジタル体験で高回収率と関係維持。延滞初日からチャージオフまで対応
-
登録日:2025-10-21
-
ソーシャルメディアとメール:
ツール情報
TrueAccord AIとは
TrueAccord AI は、機械学習を中核とするデジタル債権回収プラットフォームです。消費者に配慮したセルフサービスの体験と、行動データに基づくコミュニケーション最適化によって、エンゲージメント(関与)・コミットメント(合意)・リゾリューション(解決)を継続的に後押しします。1日遅延の早期段階からチャージオフまでの延滞ライフサイクルを一貫して扱い、第三者回収として債権者と顧客の関係性を損なわずにリキダッション(回収率)の向上を目指します。特許取得の機械学習基盤「HeartBeat」が、メッセージ内容・タイミング・チャネル選択を自動で学習・改善し、時間の経過とともに最適化を進めます。メールやウェブポータルなどの非対立的なデジタル接点を活用することで、消費者が柔軟に自らの負債を整理・清算できる環境を提供し、長期的な関係維持にもつながる回収体験を実現します。
TrueAccord AIの主な機能
- HeartBeatによる自動最適化: 行動シグナルを取り込み、メッセージの内容・送信タイミング・チャネル選択を継続的に学習・改善。
- 消費者向けセルフサービス体験: ウェブベースのフローで支払いオプションや和解条件にアクセスし、摩擦の少ない自己解決を促進。
- 延滞全期間をカバー: 早期延滞からチャージオフまで、段階に応じた回収アプローチを一貫提供。
- エンゲージメント重視の回収: 反応率と関与度を高め、長期的関係を損ねにくい方法でリキダッション向上を目指す。
- 第三者回収の運用専門性: デジタル・コミュニケーションに最適化された運用知見で、回収プロセスを効率化。
TrueAccord AIの適用ユーザー
消費者向け与信や継続課金を扱う企業に適しています。具体的には、クレジット/ローン事業者、オンライン小売・マーケットプレイス、サブスクリプション型サービス、サービス料金の後払いを扱う事業者など、延滞発生から解決までをデジタル中心に運用したい組織に有用です。債権者と顧客双方に配慮した回収体験を重視するチームに適合します。
TrueAccord AIの使用手順
- 目的と範囲の定義: 対象とする延滞ステージ(早期/後期/チャージオフ)やKPIを整理。
- データ連携の準備: 債権・アカウント属性や連絡に関する基本情報を安全に共有できる体制を整備。
- コミュニケーション方針の設定: メッセージの基調、頻度、和解条件などのポリシーを合意。
- 段階的ローンチと検証: 小規模で開始し、HeartBeatの学習と挙動を確認しながら拡大。
- 運用と最適化: エンゲージメントの変化を把握し、シナリオや制約条件を随時チューニング。
TrueAccord AIの業界導入事例
例として、消費者金融では早期延滞にデジタル接点を導入し、支払いプラン提示から合意形成までをセルフサービスで完結。オンライン小売や分割払いサービスでは、購入後の未払い発生時に、非対立的なリマインドと柔軟な決済フローで解決を後押し。サブスクリプション事業では、更新・未払いの整理をデジタルで案内し、関係維持に配慮した回収体験を実現します。
TrueAccord AIのメリットとデメリット
メリット:
- 機械学習によるコミュニケーション最適化で、時間とともに効果が向上。
- 消費者主体のセルフサービス体験により、摩擦の少ない解決を実現。
- 早期延滞からチャージオフまで一貫対応し、運用の断絶を低減。
- エンゲージメント重視で、回収と顧客関係維持の両立を目指せる。
デメリット:
- 成果は提供データの品質・鮮度に依存しやすい。
- デジタル中心のため、電話主導の回収が必要なケースでは補完策が要る。
- 機械学習の意思決定がブラックボックスに感じられる可能性。
- 業種・地域の規制や社内ポリシーに適合させるための調整が必要。
TrueAccord AIのよくある質問
-
質問1:
HeartBeatとは何ですか?
特許取得の機械学習プラットフォームで、行動シグナルをもとにメッセージ内容や配信タイミング、チャネル選択を自動的に学習・最適化します。
-
質問2:
どの延滞ステージで利用できますか?
1日遅延の早期段階からチャージオフまで、延滞の全期間を対象に活用できます。
-
質問3:
消費者側の体験はどのようなものですか?
メールやウェブベースの案内からセルフサービスで支払いオプションや和解手続きを選択でき、負担の少ないデジタル体験を提供します。
-
質問4:
導入時に準備すべきことは何ですか?
対象範囲の定義と、アカウント属性や連絡に関する基本情報の連携体制整備、コミュニケーション方針の合意が重要です。



